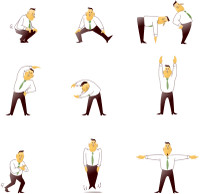2013年5月の40件の投稿
2013年5月 8日 (水)
2013年5月 7日 (火)
タケノコ掘り
ゴールデンウィーク中に知人の竹林でタケ
ノコ掘りをしてきました。といっても、今
年のタケノコは裏年だそうで、数本しか収
穫できませんでした。どうりで今年はタケ
ノコを口にしていないわけです。
外から竹林を見ると、竹の葉が黄色くて例
年ののように青々としていないのが気にな
りましたが、3、4年ぶりに入らせてもら
いました。
知人と1時間以上目を凝らして山を歩き回
ったのですが、全くタケノコの気配がなく、
穂先を見つけても皮だけになっている古い
ものや、イノシシに穂先を食べられたもの
がほとんどでした。
知人も毎年お裾分けしている常連さんがい
るそうなのですが、今年はあげられないと
残念がっていました。初物も今年は近所の
方から頂いたそうで、こんな年は生まれて
初めてだと言っていました。
私も鍬をふるえなかったのは残念でしたが、
山にいる間、ウグイスの鳴き声を近くで聞
くことができたのでとても心地よかったで
す。来年に期待しています。
工事部(資材班)岩渕敏広
2013年5月 6日 (月)
竜巻と開口部
ちょうど1年前に、茨城県、栃木県、福島県
で竜巻が相次いで発生し、1人が死亡、52
人がけがをしたほか、合わせて2000棟を
超える建物が被災してしまいました。
竜巻の時に窓などから建物の中に風が吹き込
むと屋根にかかる力が2倍になり、被害が拡
大するのだそうです。
独立行政法人の建築研究所から、竜巻の際に
建物の屋根にかかる上方向の力が計算されま
した。
その結果、窓や扉などが開いていない場合、
つまり「開口部」のない建物の場合、つくば
市を襲った竜巻に匹敵する風が吹くと、屋根
にかかる上向きの力は実際の建物に換算して
1平方メートル当たり最大632キログラム
でした。
これに対し、「開口部」がある建物では、上
向きの力の大きさが2倍の最大1,264キロ
グラムに達するということが分かりました。
つまり、窓ガラスが割れたりして「開口部」
ができると、破壊力が増すということです。
竜巻が近づいた場合には、頑丈な建物に避難
することが大切ですが、窓ガラスを雨戸やシ
ャッターなどを取り付けておくことが有効と
のことです。
経理総務部 渡辺雅彦
2013年5月 3日 (金)
地名の由来
高崎の地名の由来を詳しく紹介した、「高崎
の地名」(著者:田島桂男 発行人:株式会
社ラジオ高崎)という本があります。
著書の最初の部分には、次のように紹介され
ています。「高崎」という地名は1597年
に井伊直政によって命名されました。直政は
「松ヶ崎」としたらどうかと、竜広寺の白庵
師に相談したところ、草木には栄枯があり、
築城の成功高大の意をとって「高崎」とされ
てはどうか、と答え直政は大いに喜び高崎と
命名しました。
本文には、300ページにわたって町ごとに
紹介されています。暮らしている土地の歴史
を知ることは、暮らしていくうえで大切な心
構えなのだなと思います。
今日から大型連休の後半が始まりました。
地元のことを知る機会にするものよいかも
しれません。
経理総務部 堀口裕美子
「几帳面」
「几帳面」という言葉がありますが、この言葉
も建築から来ているそうです。
平安時代など、間仕切りや風除けに用いられた
家具「几帳」に由来し、几帳の柱の表面を削り、
細工を施した面取りを「几帳面」と言います。
几帳とは、寝殿造りの室内調度で、間仕切や目
隠しに使う屏障具(へいしょうぐ)の一つです。
土居(つちい)という台の上に2本の柱を立てて
横に木をわたし、それに夏は生絹(すずし)、冬
は練絹(ねりぎぬ)などの帷子(かたびら)をかけ
たものです。
几帳面の様な細かい装飾は、職人がきちんと正
確に作業をしなければ、美しく仕上がりません。
これが転じて、物事をきちんと行うまじめな人
を、几帳面な人と言うようになったと言われて
います。
工事部 石田卓也
2013年5月 2日 (木)
2013年5月 1日 (水)
薪焚き式風呂釜
木造の建築現場からは、たくさんの木端が
でます。ストーブ用として使っていただい
たりしていますが、お風呂を沸かす燃料と
しても使っていただいています。
こちらは、あるデイサービス施設の薪焚き
式風呂窯です。今では薪でお風呂を沸かす
のは珍しいことだと思いますが、こちらの
施設では「目玉」として使われています。
利用者の方も、薪で沸かすお風呂に入ると、
昔のことを懐かしく思い出し、喜んでもら
え、煙突から立ち上る煙を見るのが楽しみ
なのだそうです。
薪でゆっくり沸かしたお湯は、柔らかく湯
冷めしにくいそうで、あせも・かゆみも少
なくなり好評とのことです。
現場からでた木端は大きさも手頃で、使い
勝手が良いと言っていただいています。
工事部(資材班) 岩渕 敏広
「国家の計は百年にあり」と言うけれど
国民性や政治体制は百年ぐらいの歳月を経て
決まるものだという意味だと思いますが、我
が国は敗戦という歴史的な転換点を経験し、
まさに今この格言の意味を味わっています。
アジアの小国である日本が、大国である米国
を相手に戦った気骨と勇気、科学技術の高さ
に驚き「戦勝はしたけれど、この民族をこの
ままにしておくのは非常に危険である」とい
うことで、マッカーサーは日本人から大和魂
をなくすことを使命として赴任されたと聞い
ています。
教育勅語を禁止させ、天皇制を廃止して極端
に左傾した人たちに教育を指揮させて、もの
の見事に大和魂を消し去ることに成功しまし
た。
六十八年たった今、教育基本法の見直しが論
議され始め、小学教育に道徳の教科を復活さ
せるようですが、その成果が現れてくるのは
四十~五十年先です。
礼儀を重んじて社会秩序を考え、日本人とし
てのアイデンティティーを大切にする…
世界中の人々から本当に尊敬される国になる
までにはまだ多くの時間が必要です。
まさに「国家の計は百年にあり」であります。
by=小井土 靖