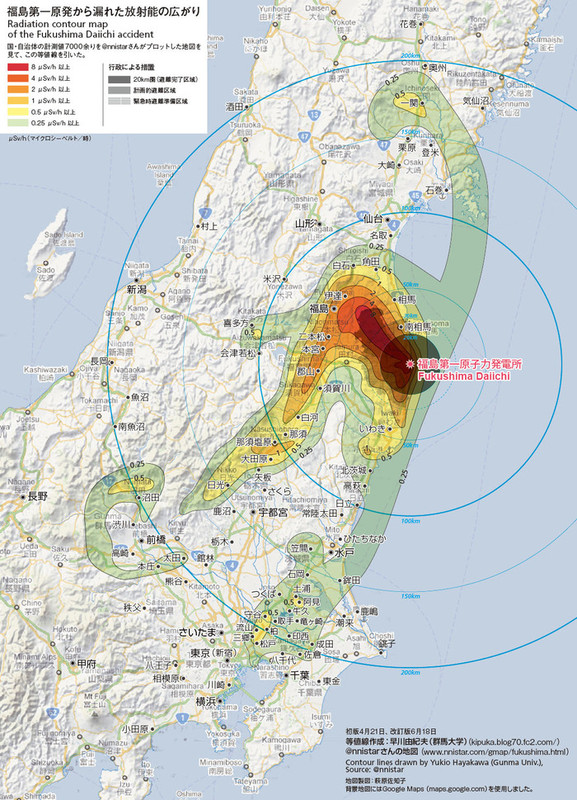放射性廃棄物保管のガイドライン
環境省は、国による処分が来月以降に始まる
までの間、市町村が廃棄物を保管するための
具体的な方法をまとめたガイドラインを12月
25日に公表しました。
放射性セシウムを含む汚泥やごみの焼却灰
などの廃棄物のうち、濃度が1キロ当たり
8000ベクレルを超えるものは、特別措置
法に基づいて国が来月以降、処分を行うこと
になっています。しかし、国が処分を始める
までの間は、各自治体が保管を求められるこ
とから、環境省は、放射性物質が地下水にし
みこんだり、火災が起きたりしないための積
み上げ方など、具体的な保管方法をまとめた
ガイドラインを公表したというわけです。
国が処分場を確保するまでは、自治体によ
る保管が続くことになり、住民の理解をどう
得ていくかが課題となります。また被災地の
がれきのうち、放射性セシウムの濃度が、1
キログラムあたり3000ベクレル以下のコ
ンクリートについては、30センチ以上埋め
れば、同じ県内で道路や防波堤などに再利用
できるとする基準も示されました。
一時保管にしろリサイクルにしろ、定期的に
放射線量を測定することが大事だと思います。
特に、子どもたちの身の回りで放射線量が高
くならないように最大限の注意を払う必要が
あると思います。
経理総務部 渡辺雅彦